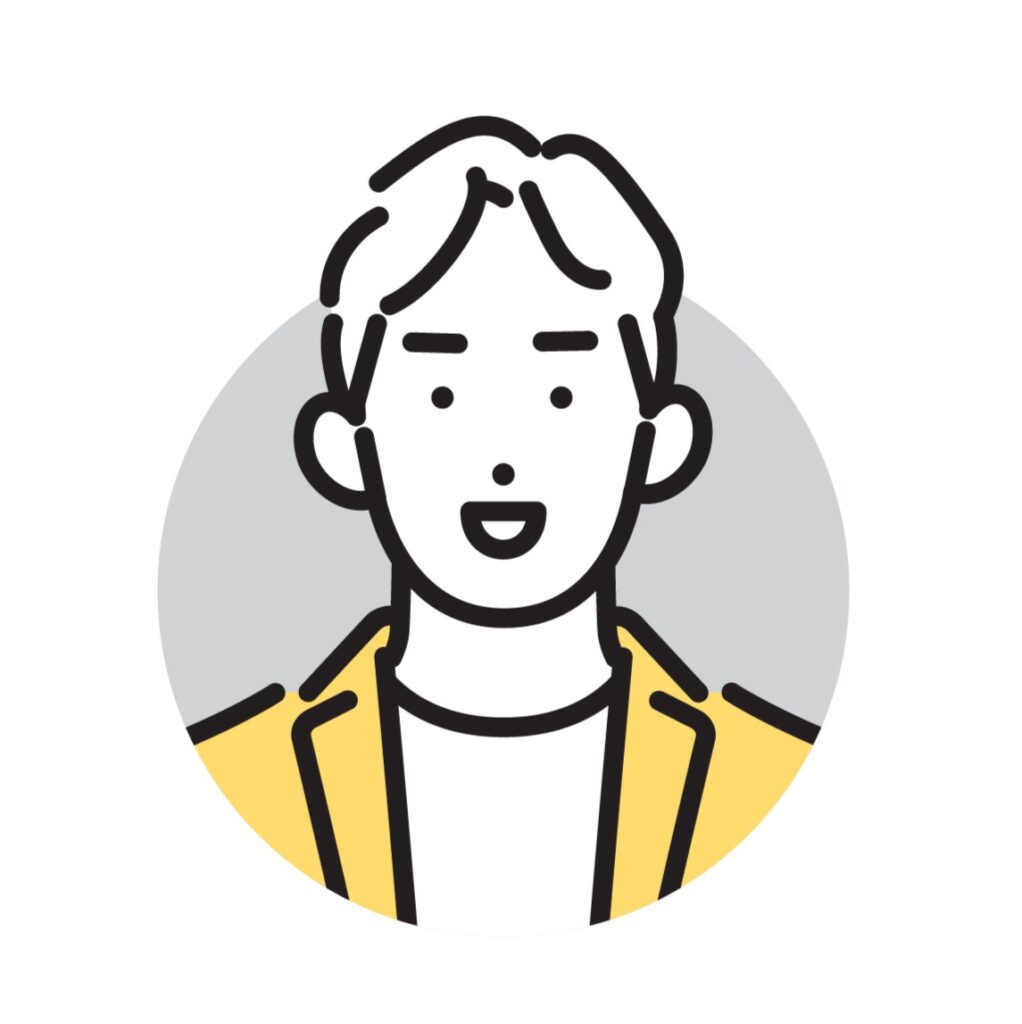参加者の声
Participant's Voice
いざというときに、全国に支え合える仲間がいること。
それが、私たちの強みです。

受講者インタビュー
Participant's Voice
小坂 律子
kosama rituko
石川県
今日、特に心に残ったのは、Kさんのご自宅の備蓄を写真で見せていただいたことです。
実際にKさんの備蓄を拝見し、「これくらいあれば十分だろう」と考えていた自分の備えが、いかに不十分であったかを痛感しました。
正直なところ、私が想定していた量の10分の1程度しか準備できていないと感じ、ハッとしました。
また、今日話題にのぼった「井戸水」についても、改めて学びになりました。

私の実家では、昔は井戸水を飲み水として利用していました。しかし水質検査の結果、「飲料には適さない」とされ、今では外で手を洗う程度にしか使っていません。
そのため、「もし何か起きたときに、この水は本当に飲めるのだろうか?」という不安が常にあります。
今日、同じグループのIさんから、山からホースで水を引く方法や、「汚れが入らないようにするための工夫」についての知恵も教えていただき、具体的にどのような対策ができるのかが少し見えたように感じています。
「ペットボトルを重ねてろ過する」といった、実際に行動に移せるアイデアもあり、ただ備蓄するだけでは不十分で、“いざという時”に備えた知識と実践の両方が大切なのだと、あらためて実感しました。

蛇口をひねれば水が出る生活が当たり前ですが、これからの時代、危機感を持って「学ぶ」ということが不可欠だと思いました。備蓄だけでは限界があり、その備蓄も使えない可能性すらある。そうした時に生き抜くための知恵とスキルが必要です。
たとえば、Iさんのところに実際に学びに行くとか、今日話に出てきた「ロケットストーブで火を起こす」など、私自身まだまだそこまで生活スキルが伴っていないと感じました。今回のウェビナーをきっかけに、まずは知ること、学ぶことから始め、次のステップへ進んでいきたいと思いました。
石丸 仁志
Isimaru hitoshi
山口県
私は山口県の山の上に住んでいます。現在、近くの放棄された田んぼを、仲間たちと共に草刈りから始めて、運搬や耕作をしながら田植えを行っています。
まだ始めたばかりですが、自分たちの手で食べ物を育てていくことで、「何かあっても大丈夫だ」という安心感が少しずつ芽生えてきていると感じています。逆に言うと、食べ物が手元にあると、過度な危機感にとらわれなくて済むのかもしれません。

ただ、やはり災害が起こると、真っ先に失われるのは電気だと思っています。そのときに、どうやって快適に暮らす工夫をしていくかが、これからの大きなテーマになると考えています。
水については、山の上にある沢の水を活用しています。200リットルのタンクに一度水をため、その水圧を利用して、凍結に強い農業用ホースで300メートルほど引いて、道のそばまで流す仕組みを作りました。手間はかかりましたが、いざという時のために非常に安心感があります。
まだ田んぼの作業は本格化していませんが、田んぼ(米作り)をするにも、水は大切な資源です。これからも、皆さんと学びを高め合いながら、電気がなくても水と食を確保できるような暮らしを目指していきたいと思います。



片岡 徳久
kataoka norihisa
奈良県
奈良で「アースリング」という市民団体を運営している片岡です。私たちは、現在、会社から車で30分ほどの場所にある古民家(14LDK)を活用し、二拠点生活をスタートさせています。
広い古民家で、ここに社員とその家族の分も含めた、3ヶ月~6ヶ月分の生活物資を備蓄しています。
水・電気・トイレなどのインフラも一つずつ整備しており、災害用伝言ダイヤルの使い方や、各自の貴重品リストなど、災害時の対応マニュアルも全員で共有しています。

また、最近では皆で草刈りをしたり、DIYで住環境を整えたりと、暮らしそのものを「楽しみながら」実践に移しています。ようやく井戸も使える目処が立ち、いよいよ自給的な暮らしに一歩ずつ近づいてきました。
今後は、畑の数も増やし、地域の方々と協力しながら、共助のネットワークを広げていきたいと考えています。智さんは丹波で素晴らしい取り組みを進めておられ、農業関係の専門家との繋がりも豊富にお持ちになられています。私たちもぜひアドバイスをいただきながら、奈良の地でも「自助・共助・公助」がバランス良く成り立つコミュニティづくりを目指していきたいと思っています。
郡司掛 一輝
gunjikake kazuki
大阪府
オンライン勉強会の話を聞いて、「知っているようで実は知らなかったこと」がたくさんあるなと改めて思いました。とても勉強になりました。
実は横で妻も一緒に参加していたのですが、「こういうことって実際に災害現場に行かないとわからないよね」と言っていて、本当にその通りだなと感じました。

やはり実際に被災地に足を運んでこられた方だからこそ語れる、現場から得たノウハウだと再確認できて、非常に有意義な時間でした。
ここに参加されている方々は、情報感度が高く、報道などでも活躍されている方が多いと思います。
そんな皆さんがつながって、互いに助け合っていけるような世界が実現すれば、すごく希望が持てるし、僕もこの活動が広がるように一緒に動いていきたいと思いました。ありがとうございました。
有田 由樹子
arita yukiko
兵庫県
防災対策と聞くと、どこかで「子どもがいる家庭が中心に考えること」と思っていました。
私は、1人で身軽に動けるし、「なんとかなるかな」「困ったら、避難所に行けばいいかな」と、どこか他人事のように捉えていたんです。
でも…
・自分が今住んでいるエリアで想定されている災害は?
・自宅でどのくらいの備蓄が必要なのか?
・もし停電が数日続いたら? 水が止まったら?
そんな問いを受け取る中で、「もっと考えないと…」と考えるようになりました。

特に印象に残っているのは、「誰かを守るために備えることは、自分自身を守ることにもつながる」という言葉です。
備えがあれば、職場の同僚や近所の人と助け合うこともできる。逆に、無防備だと、周囲に迷惑をかけてしまう…。そう思ったとき、自分一人の問題ではないんだと気づきました。

勉強会では、知識を学ぶだけでなく、実際の被災事例やケーススタディが豊富に紹介され、とても実践的で分かりやすかったですし、「どんな環境にいる人にとっても、防災の備えは不可欠だ」と実感しました。
今では、友人にも「防災対策してる?」と声をかけるようになりました。
「もしものときの安心」は、日々の行動からしか生まれない——
そのことを教えてくれた皆さんに、心から感謝しています。
北川 義和
kitagawa yoshikazu
大阪府
私は仕事で、リスク管理や経営計画、社員の福利厚生などに関わることが多く、地震や台風といった自然災害への備えについても、それなりに意識してきたつもりでした。
ですが、勉強会に参加してみると、これまで自分が「理解している」と思っていたことが、実は断片的な知識にすぎなかったことに気づかされました。
講座では、防災に関する情報が一つひとつ丁寧に整理され、点だった情報が線でつながる感覚がありました。
その中で、「だからこの備えが必要なんだ」と、腑に落ちる瞬間が何度もありました。

特に心に残っているのは、「災害時に本当に起こる“想定外”とは?」というテーマでした。
自分ではイメージしていたつもりの状況でも、
「情報が錯綜して判断ができなくなる」
「家族と連絡が取れない中で、誰をどう優先するか」
――そんなリアルな問いに触れたとき、胸をつかまれるような感覚がありました。
災害時の混乱の中で、本当に正しい判断ができるのか?
そのとき、自分はちゃんと動けるのか?
その問いは、今でも深く心に残っています。

また、災害時「自分は社会の中で、どんな役割を果たせるか」という視点も与えてくれました。
防災は、自分の身を守るだけでなく、地域や職場、社会全体で取り組んでいくもの。
「自分さえ無事ならいい」ではなく、「自分はどう関わっていけるか」を考えることの大切さを、改めて実感しました。
“防災”が、ただの知識から、行動へ。
そして今では、ちょっとした使命感のようなものに変わってきた気がします。
まだまだ完璧ではありませんが、まずは家族との会話を増やしたり、地域の防災訓練にも参加してみようと思っています。防災に関心はあるけれど、何から始めたらいいか分からないという方こそ、ぜひ一度この講座を受けてみてほしいです。
きっと、自分なりの気づきや、一歩踏み出すきっかけが見つかると思います。

事務局からのメッセージ
Message from the Secretariat
青木 佑介
aoki yusuke
日本社会づくり協議会 本部事務局
災害が多発するこの時代において、「自分と家族を守る力を、一人ひとりが高めていくこと」が本当に重要です。
それは、ただ不安だから備える、ということではなく、「誰かのために、自分が動ける状態になっておくこと」が、これからの社会を支える土台になると信じているからです。
これまで日本は、幾度となく大きな災害や困難に見舞われてきました。しかしそのたびに、地域や仲間、そして見ず知らずの人との「助け合い」の力で乗り越えてきました。
その精神は、私たちの中に確かに根付いています。

「自分さえ助かればいい」ではなく、一人でも多くの命を守るために、まず自分が備えておく。そんな視点が、今こそ大切になってきているのだと思います。
協議会が発行している手引書やe-Learning教材では、日常の中で実践できる防災の知恵を総合的に学ぶことができます。さらに、定期的に開催しているオンラインセミナーでは、全国の会員さん同士がつながり、意見を交換し、学び合う場があります。
地域や年齢、職業が違っても、同じ想いで集まった人たちと顔を合わせて学ぶことで「自分は一人じゃない」と感じられる。そして、そのつながりが、いざという時に“命を守るネットワーク”へと変わっていく――そんな力を感じています。

私たち事務局も、ただ知識を届けるだけでなく、皆さんと一緒に学び合い、備え合い、支え合える関係を築いていきたいと願っています。
将来的には、大きな災害が起きたとき、各地の会員同士が連携し、助け合える――
そんな「共助の仕組み」をつくっていきたいと考えています。
一人では不安なことも、仲間とならきっとできる。
そんな未来を、一緒に育てていきませんか?
この想いに少しでも共感していただけたなら、ぜひ一歩を踏み出して、ご参加ください。
あなたのその一歩が、きっと誰かの命を守る力になります。
心より、お待ちしております。